人の視覚は、炎天下の非常に明るい環境から、新月の星明かりの非常に暗い環境まで、自然環境の幅広い明るさに対応しています。これは人の視覚が、視野に捉えた明るさの違いでモノを認識しているからです。一方、人の目は視野の全体的な「明るさの量」を認識する能力には優れていません。昼と夜といった大きな明るさの違いは簡単に認識できるのですが、昼間の多少の明るさの違いは、よくわからないのです。
その場所の全体的な明るさに関係なく、明るいところと暗いところといった、相対的な明るさの違いを検出するように進化した視覚にとって、明るさの“量”の知覚は、不得意なのです。
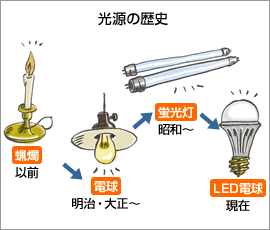
とはいうものの、私たち人間は、明るさを求めて照明技術を発展させてきました。夜の闇を部分的に照らすことから始まり、光を強くしていくことで相対的に明るい場所を獲得し、次第にその範囲を広げていったのです。
時代によって光源の種類は、灯火や蝋燭から石油ランプ、ガス燈、電燈へと移り変わりますが、新たな光源が登場するたびに、それは「太陽のような輝きの光源」と評判になりました。そして、新光源の出現によって、それ以前の光源は「暗くて古いもの」と見なされるようになります。というのも、新しい照明が出現したばかりの頃、周囲はまだ以前の光源ばかりです。
新光源の明るさは、それまでの光源との対比によって、抜きん出て明るく感じられるのです。しかし、新たな光源が普及して、周りがすべて新しい光源になると、人の目は明るさに慣れ、対比効果が失われます。「太陽のような輝き」と感じた光源も、それほど明るく感じられなくなります。そして、また新たな明るさを求めて光源が開発される…。この繰返しで、どんどん明るい光源を求め続けて来たのが、光源の歴史です。
光量の増加は、作業性を向上させました。また、光源が安く手に入るようになったことで、昼間しかできなかった労働が夜間へと延長され、作業時間の延長とさらなる生産性の向上をもたらしました。明るさは豊かさに直結するものと認識されるようになり、豊かで快適な暮らしの象徴になったのです。
20世紀になり、電気照明の普及による配電網の整備に伴い、電力の大量消費時代を迎えます。夜間の室内も、スイッチ一つで闇を消し去ることができるようになりました。安価な電気と器具の普及によって、限られた範囲を照らす局部的な照明から、空間全体を照らす全般照明へと、時代は移行していきます。
局部的な照明では器具の光量が増すと、その輝きはまぶしさを産みます。そのため、「光源の光量は大きいほど良い」というわけではありません。しかし、全般照明のもとでは、人の目は明るさにすぐ順応し、局部照明ではまぶしく感じるような光源もまぶしさを感じません。そして、もっと明るい環境を求めて、光量の大きな光源を求めるようになります。
こうして一部の建物、一部の空間が明るくなると、対比効果によって他の空間が暗く感じられます。すると、暗く感じる空間は、光量を増やすことで明るさを得ようとし、次々と周囲が明るい空間に染まっていきます。そして全体が明るくなると、また、さらに明るい空間が出現します。このように、人の目は対比効果と順応の繰返しで、徐々に明るい光源を求め続ける性質があるのです。
明るさを求め続けた結果として、21世紀初頭の照明された屋内では、もはや闇は駆逐され、屋内全体が明るさで満たされています。そして、それは夜間の都市照明へと広がっています。
人の視覚は、どこまで明るさを求め続けるのでしょうか。
そのひとつの答えは、昼間の太陽の明るさです。人の目はおそらく、真昼の直射日光の下での光環境を超える光量を求めることはないでしょう。そして、現状では技術的・コスト的な制約によって、そこまで至ることはありません。
でも、もしそれが可能になったとして、本当にそれほどの光が必要なのでしょうか。真昼の直射日光の下でなくとも、人の視覚は、昼間の木陰や森の中の光環境でも充分に機能します。そして、このような光の下でこそ、心地よさを感じるのではないでしょうか?
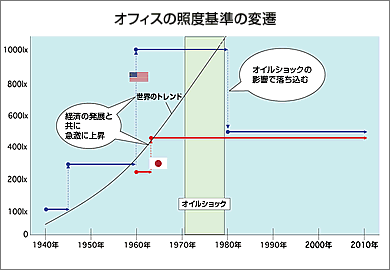
室内照明の基準は、心地よさとは別に経済的な要因で決められてきた経緯があります。
オフィスの照明の照度基準は、1940年頃は100lx程度(ロシアでは40lx)で、1950〜60年頃には300lx程度になり、1960年頃の北米での1000lx程度でピークを迎えます。その後、オイルショックなどのエネルギー危機を経て、1990年頃には500lx程度に落ち着き、現在に至ります。それでも当初の5倍の明るさです。オフィスの作業性ももちろん考慮しなければなりませんが、一旦1000lxまで高く引き上げた照度を、上手に低く誘導できているのかは、疑問が残ります。
人の目の機能と照明技術の進歩を考えると、現状の照明の明るさは、充分すぎるほどの光量が実現されています。全体をまんべんなく照らすのではなく、明るさにメリハリをつけ、明るさの分布をうまく制御することで、照度を低くしても充分に明るく感じる環境が得られると思います。
2011年夏の節電では、基準よりも低い照度でも「案外イケル」との話題が良く上がりました。「全体の明るさの“量”を知覚することが苦手」という人の目の特性を上手に利用すれば、もっと「案外イケル」光環境が実現するのではないでしょうか。

(関西大学 環境都市工学部 建築学科 原 直也)